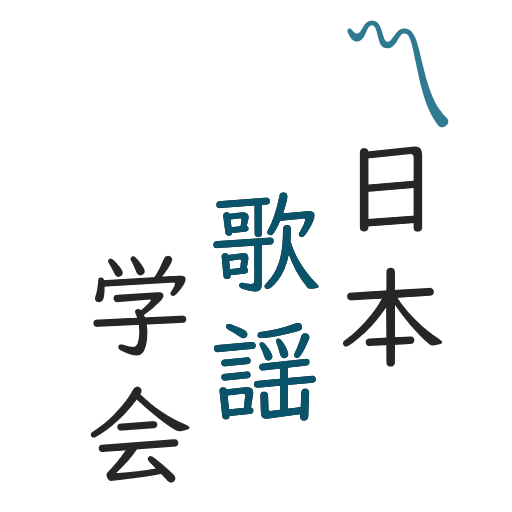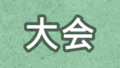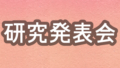終了しました。
| 期日 | 令和6年 5月18日(土)19日(日) |
| 会場 | 清泉女子大学(Zoom併用) |
公開シンポジウム
1日目 18日(土)
13:00~17:30 1号館4階 140教室
●開会の辞 日本歌謡学会会長 清泉女子大学 姫野敦子
●会場校挨拶 清泉女子大学 学長 佐伯孝弘
●シンポジウム 今様「足柄」をめぐる総合的研究
総合司会 共立女子大学名誉教授 菅野扶美
・基調報告 今様琵琶譜の文学・文化的意義
金沢大学 猪瀬千尋
・報告1 「足柄」の位相 元杉野服飾大学教授 馬場光子
・報告2 国語史からみた足柄琵琶譜 島根大学 浅田健太朗
早稲田大学 加藤大鶴
・報告3 院政期における琵琶譜の機能と役割―〈足柄〉三首の分析から
京都市立芸術大学 特別研究員 根本千聡
・「足柄」三曲の復元演奏
・全体討論
●日本歌謡学会志田延義賞授賞式
研究発表
2日目 19日(日)
10:00~17:00 1号館4階 142教室
●研究発表 午前の部(10:00~12:10)
1、念仏剣舞における山の和讃の機能性 国際仏教大学院大学大学院生 杉山兵介
2、民俗芸能における歌謡の音楽構造が奉納準備と継承者育成へ及ぼす影響
――鹿児島県いちき串木野市羽島崎神社の奉納歌謡「羽島舟唄」の事例を中心に――
鹿児島大学法文学部特任専門員 片岡彰子
3、こゆるぎ大明神のために ――こいその翁異聞――
神奈川県立総合教育センター非常勤職員 鈴木信太郎
●研究発表 午後の部(13:10~15:20)
1、「来目歌」から久米舞へ――『日本書紀』と『続日本紀』の比較を通して――
立命館大学大学院生 砂田和輝
2、カタオロシの機能について――歌われた場からの考察――
天王寺学館高等学校非常勤講師 福原佐知子
3、久米歌の歌い方とそれが意味するもの 歴史民俗博物館名誉教授 小島美子
●総会(16:00~16:30)
●閉会の辞 立命館大学 辻浩和
※春季大会に対面で参加ご希望の方は、以下のURLのグーグルフォームからお申し込み下さい。下のQRコードからもアクセス出来ます。
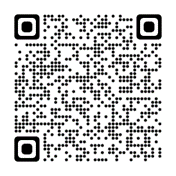
リモート参加の方法等は、ご希望の方に順次Eメールにてご連絡いたします。
※学会当日は、学内で保護者懇談会、オープンキャンパスなどの催しが行われています。会場を間違えやすくなっていますので、お気をつけ下さい。1号館地下1階の清泉カフェが営業しており、コーヒーや手作りのピザやお菓子を売っております。もしよろしかったらご利用ください。
【問い合わせ先】
日本歌謡学会事務局
〒141-8642 東京都品川区東五反田3-16-21
清泉女子大学 姫野敦子研究室内
E-mail nkayoug2022★gmail.com メール送信の際は★を@に変換してください。
シンポジウム「今様「足柄」をめぐる総合的研究」趣旨
宮内庁書陵部に所蔵される『諸調子品撥合譜』には、今様の秘曲「足柄」三首と、「物歌」一首が収録される。従来、表題のみが知られていた足柄の歌詞がわかったことは、文学史上、大きな意義を持つものと考えられる(猪瀬千尋「新出今様琵琶譜 足柄三首、物様一首」『国語と国文学』96-10、2019年)。
しかし本譜発見がもたらした問題は、歌詞のみにあるのではない。『諸調子品撥合譜』の足柄歌は、琵琶譜で記されている。今様が歌われていた時代に残る、唯一の楽譜である。かつそれは日本音楽史上、最も重要な人物の一人である藤原師長(1138~92)の自筆譜原本である可能性すらある。それは当時の歌い方やアクセントの問題にも及び、つまるところは音楽としての復元の問題にも及ぶ。『諸調子品撥合譜』は、日本文学の方法のみでは太刀打ちできない、多様な可能性を持った書物なのである。
本シンポジウムでは、それぞれ異なる専門(文学・日本語学・音楽学)である研究者の報告により、この希代の楽譜が持つ学術的意義について、踏み込んだ検討を重ねてみたい。
基調講演 今様琵琶譜の文学・文化的意義
金沢大学 猪瀬千尋
『諸調子品撥合譜』について、その書物としての意義と、歌詞(足柄)から読みとれる意義について述べたい。
まず書物の形態から問題を提起する。『諸調子品撥合譜』は天三条地一条の界線を持つ。即ち上部に3本、下部に1本の墨線が引かれる。これは中世の琵琶譜では一般的な形であるが、本譜がその原型であった可能性がある。
かかる琵琶譜の基礎をつくったのが藤原師長(1138~92)である。師長は様々な歌謡の琵琶譜化を試みていた。例えば師長作の譜の一である書陵部蔵『高麗曲等譜』(伏980)には、『拾遺和歌集』所収の素性法師の和歌「あらたまの としたちかへる……」の和歌琵琶譜が記されている。和歌被講譜の初例をはるかに遡る貴重な例といえる。師長のこうした声の楽譜化の営みは、声明とも連続する。この点は『三五要録』巻13と、守覚法親王・多近久撰『風俗譜』などから述べることができよう。
一方、歌い手である後白河院(1127~92)にとって、足柄はどのような意味を持つのであろうか。足柄は恋歌に近しい歌である。必ずしも神妙とは呼べない歌を、後白河はなぜ神仏の御前で真っ先に奉納したのか、この点について『梁塵秘抄口伝集』末尾の記述や、『撰集抄』所収の江口の遊女の話などから考察する。
報告1 「足柄」の位相
元杉野服飾大学教授 馬場光子
平安朝後半に、都で大流行した新風の歌謡「今様」。そのジャンルは広く、なかでも大曲(だいごく)(秘曲)とされた「足柄」十首の原曲が歌えるかどうかが、伝承の要とされた。
歌の伝承者は、美濃國の靑墓の宿の傀儡の女性とされる。東国からの文化のあらゆるものが、都を前に、比良山系鈴鹿山系に阻ばまれ、人馬とともに足柄文化圏の歌謡も、一旦この宿に留められたのであろう。
ごく最近まで、「足柄」十首のうち、「恋せは」という名称の歌詞一首だけが伝えられてきた。しかし、猪瀬千尋による『諸調子品撥合譜』の発見により、「関神」「瀧水」「恋者」の歌詞が明らかになった。ここより、都が新たに受け入れた地方性の強い「足柄」の特性が浮かび上がってくる。
またこれが妙音院流の琵琶譜であることにより、旋律が甦る可能性が生まれ、「足柄」に身体的に丸ごと触れることができると思うと、感慨深い。
報告2 国語史からみた足柄琵琶譜
島根大学 浅田健太朗
早稲田大学 加藤大鶴
本発表では、『諸調子品撥合譜』に含まれる足柄琵琶譜を国語史の観点から分析し、その資料性、譜の特徴、アクセントとの関わり等について述べる。
まず仮名字体について、訓点資料および片仮名文資料との比較を行いながら、使用者や時代について検討を行う。同時に識語についても、他資料との比較から先行説を検討し、さまざまな可能性を提示したい。
また足柄譜と同様に歌謡と関連する琵琶譜として、声明の琵琶譜である『声明譜 琵琶』(建暦元年(1211)藤原光孝写、西園寺実兼補筆、宮内庁書陵部蔵、伏・980、https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100248841/)を取り上げる。同じ妙音院流の節博士譜である、『声明類聚』(鎌倉時代後期写、旧金沢文庫蔵釼阿手沢本、前田尊経閣文庫蔵)と比較し、歌謡の譜本として琵琶譜が使用されている事例として記譜法を考察することによって、足柄琵琶譜の内容について検討する。
さらに、琵琶譜と本文の関係を見ることによって、詞章と節付の関係や囃子詞、アクセントとの関連に言及したい。
報告3 院政期における琵琶譜の機能と役割―〈足柄〉三首の分析から
京都市立芸術大学日本音楽伝統センター 根本千聡
院政期において琵琶道を極めた藤原師長は、あらゆる楽説を集成した琵琶譜『三五要録』を編んだ。師長は絃楽器のみならず歌謡にも精通していたと伝わり、その証左の一つとして、同書の巻三・四には催馬楽の譜が収められている。これは歌の旋律を琵琶の譜字であらわしたもので、具体的な音楽を今に伝える貴重な資料となっている。
今回取り扱う『諸調子品撥合譜』中の今様譜も、そうした催馬楽譜と同様、師長によって作られた可能性の高い、歌の旋律を琵琶の手に置き換えた譜である。本資料の発見により、絶伝した今様〈足柄〉三首の旋律の復元を試みることが可能となった。本発表では、当楽曲の復元作業および楽理的な分析を通じ、その音楽的特徴の一端と、多様な音楽を琵琶譜によってあらわすことの意義や文化的背景について検討をおこなう。
研究発表要旨(午前の部)
【研究発表1】念仏剣舞における山の和讃の機能性
国際仏教大学院大学大学院生 杉山兵介
本発表では発表者が継続的に調査してきた〈念仏剣舞〉の歌謡から山の和讃をとりあげ、夭折の亡者への供養と現世の人びとへの哀愍という思想を論じる。
念仏剣舞は東北地方に分布する念仏踊の一種であり、とくに岩手県に散在する。念仏剣舞の歌謡は踊りに伴う踊り歌、供養を主眼とした和讃、そして短い詞章に六字名号を付加して祝言する誉め歌の三種に分類される。念仏剣舞における念仏の意味に注目するとき、とりわけ重大な対象となるのが和讃と誉め歌である。本発表では和讃の事例から「山の和讃」と筆者が便宜的に仮称する歌謡を検討する。
山の和讃は念仏剣舞における和讃のなかでもポピュラーな一例であり、多くの歌本や見聞録に見出される。特に菅江真澄が『鄙廼一曲』に収録したことから、柳田國男はこれを非仏教的な霊山地獄信仰を伝える手がかりと評価し、森山弘毅は春の訪れによって達成される富士登頂の心情を表現する歌謡と解釈した。本発表では従来の研究や類歌を参照しつつ、この和讃の成立と分布、解釈を巡る検討点と所見を呈出し、より詳細な註釈を編んでみたい。
山の和讃は諸地域の念仏講や念仏踊にも用いられ、近世和讃のひとつとして流行した作例であることが推測される。また、詞章を分析すると天折した亡者を供養の対象にしつつ、親に念仏を捧げるべしとする志向や、現世往還の祈願といった要素が認められた。こうした性格には鳥獣にまつわる民間習俗との関連性、近世に流行した孝の影響がうかがえる。そのうえで、念仏剣舞そのものの機能に夭折の亡者への哀愍と現世往還が祈願されていることを指摘し、近世和讃の一例である山の和讃が、念仏剣舞という特殊な領域においてどのような歌謡として位置づけられるかを論じる。
念仏剣舞の歌謡は翻刻紹介が多くなされてきたが、学問的な研究事例に乏しい。鄙見を通じて先生方からのご批判を乞いたい。
【研究発表2】民俗芸能における歌謡の音楽構造が奉納準備と継承者育成へ及ぼす影響――鹿児島県いちき串木野市羽島崎神社の奉納歌謡「羽島舟唄」の事例を中心に――
鹿児島大学法文学部特任専門員 片岡彰子
薩摩半島に広く見られる棒踊り、太鼓踊り、及び羽島地区に残る舟唄といった民俗芸能では奉納の歴史・文化に関する研究は厚いが、稽古の様子を含めた調査研究は少ない。発表者は練習現場で参与観察と聞き取り調査を行ううちに歌謡の音楽構造が歌唱者達の様々な行動と密接に関わっていることに気づいた。そこで音楽構造が歌唱者の奉納準備と継承者育成という課題とどう関わるのかを稽古に着目して考察した。
棒踊りは歌に合わせて踊り手達が長い棒を打ち合う踊りで、太鼓踊りは鉦や太鼓を鳴らしつつ隊形を変えていき、歌を伴う曲もある踊りである。羽島舟唄は男声二声部が交替しながら歌い継ぐ集団歌唱である。独唱である棒踊りや太鼓踊りの場合、節回しを含む歌唱表現と歌の習得は二人いる歌い手の各々に任されている。継承では二人同時の代替わりは避け、一人は残って新人と共に踊りとの合同練習及び奉納を行う。総じて歌い手の自主独立を重んじていると考える。一方集団歌唱の羽島舟唄の場合、節回しは細部まで定型で全員がぴたりと合わせて歌い、かつ声部の交替では互いに少し重ねて歌い出す技法を用いるため合同練習が不可欠である。さらに毎年一定の仕上がりで奉納できるよう、歌い手の各役割は代替が効くように稽古をしている。また全十一曲の各々が詞章も節も異なり様々な歌唱技法を含むため、新人は初年度から奉納に参加するが声を張って歌えるまでに数年かかるものとして臨んでいる。奉納では船の形に隊列を組み、新人はベテランの歌い手に挟まれるように配され、前の人の所作を見て真似、後ろの人の声に自分の声を合わせる事で歌い方を覚えていく。この数年かけて新人を一人前に育てるという継承方法は舟子の育て方に類似すると考える。
このように民俗芸能における歌謡の奉納準備と継承者育成の方法は各々の音楽構造に合ったものであり、かつ背景にある文化が稽古のあり方を規定するという側面もあるといえる。
【研究発表3】こゆるぎ大明神のために ――こいその翁異聞――
神奈川県立総合教育センター非常勤職員 鈴木信太郎
尊経閣文庫蔵『今様の濫觴』では、「相模国こいその翁」について「而宿」における今様の始源譚として語られる。しかし、その実像は資料的制約から不分明であり、言及される際には、今様「足柄」あるいは「足柄明神」に包摂して論じられることが多いようである。資料の残存状況や今様の研究史からすれば、このような仕儀になるのはやむを得ず、首肯できることと考えられるが、前々から少々気になることがある。そこで本発表では小磯の翁像について、寺院の年代記等の中世神話的な記録類も参看しながら推測を試みてみたい。
『今様の濫觴』では、「相模国こいそ」は、現在の神奈川県大磯町の小磯付近と比定してほぼ間違いないと思われる。一方、『万葉集』、『古今和歌集』さらには『風俗』にも、「こゆるぎ」という地名を用いた歌謡群が残されている。「こゆるぎ」は、小磯を包含する相模湾海辺域の大地名として古来歌枕などとして頻用されている。「こひそ」についても、特定の地名を指示しないと解されつつ『梁塵秘抄』などの今様に散見される。
そしてそのことから、海神を背景とした海辺の歌や歌謡の大きな群と、それを取り巻く説話群の存在を推測できるであろう。「相模国こいその翁」もこうした海辺の歌謡圏の伝承者の一人として捉えることができるのではなかろうか。
一方、「相模国コユルキノ大明神」というその地方の地誌を繙いても見かけることのできない神名を、興福寺累代の出来事を記した『興福寺略年代記』(群書類従本)の中に見出すことができる。この大明神が「こゆるぎ」の地で奉斎されていた神名と考えられるとすれば、足柄明神と次のような対偶関係を形成していることが想定できないだろうか。
今様「足柄」――足柄の翁――足柄明神 ――山神
海辺歌謡群 ――小磯の翁――こゆるぎ大明神――海神
最後に、『今様の濫觴』に立ち返り、今様「足柄」の相承の中で語られる「小磯の翁」の意義について考察してみたい。
研究発表要旨(午後の部)
【研究発表1】「来目歌」から久米舞へ――『日本書紀』と『続日本紀』の比較を通して――
立命館大学大学院生 砂田和輝
発表者は前回、令和五年度日本歌謡学会春季大会の発表において、『日本書紀』に記される「来目歌」の前に記された「手量」の語の用例を検討し、この語が舞の動作を示すものであると指摘した。ただ、後世に散見する久米舞というような名称が『日本書紀』には見いだせないという問題点についてその理由を十分に検討できていなかった。この点を明らかにするために、今回の発表では舞について記された古代の記事を確認し古代における舞の収集、教習などの整備過程が歌のそれよりも遅れてなされていたことに触れながら考察する。
古代において舞を管轄していたのは701年に創設された雅楽寮であるとされるが、『続日本紀』において名称が記される舞は諸県儛、筑紫儛、五節田儛、久米儛、楯伏、蹋歌、袍袴の七例で、『日本書紀」の殊儛(立出儛)、伎楽儛、八佾儛、田儛、小墾田儛、楯節儛の六例と比べてもその差は大きくない。また、諸県儛、筑紫儛については天平3年7月(730年)の記事にその生の数が定められたとあり、雅楽寮の創設から約30年遅れていることが確認される。さらに、『続日本紀』には隼人が上京し歌舞を奏上したとする記事が四例みられるが、どれもクニブリ(風俗、土風)の歌舞とされ後世の文献に散見する隼人舞の名称はみられない。このように、雅楽寮が創設された後も筑紫儛はまだ教習の途上であり、隼人舞に至ってはいまだ教習に至っていないものと推察される。 『令義解』にみえる職員寮の項では大陸由来の楽を雅曲正儛、それ以外のものを雑楽としており『日本書紀』にみられる伎楽儛、八佾儛は前者に属する。すなわち、宮廷の儀礼や祭祀で奏上される雅曲正儛については7世紀の時点で既にある程度整備されていたと考えられる。これに対して、雑楽に属すると考えられる久米舞は筑紫舞や隼人舞の例に鑑みてその教習にも時間を要したものと考えられ、『日本書紀』にみられる「来目歌」よりも遅れて『続日本紀』に記載されるに至ったということを論じる。
【研究発表2】カタオロシの機能について――歌われた場からの考察――
天王寺学館高等学校非常勤講師 福原佐知子
カタオロシの歌曲名は、古事記に「夷振之片下」、琴歌譜に「片降」、東遊歌に「加太於呂之」がある。本居宣長『古事記伝』は、「片下は上の尻上歌(シラゲウタ)上歌(アゲウタ)、などの上(アゲ)と相照して心得べし、上(アゲ)も下(オロシ)も歌ふ音振(ネブリ)を以て云なり、片(カタ)とは三句の歌を片歌と云如く、本にまれ末にまれ片(カタガタ)を下(オロ)してうたふなるべし」と述べ、アゲと対になるオロシの音振のこととする。宣長は鍋島家本『東遊歌神楽歌』の裏書に拠っているのであり、「神楽歌古本に云々、次薦枕静歌【拍子十本末各五】尻上【拍子十四本末各七】又【裏書】以前木綿志天前張、此三首各静歌二返、尋琴拍子打、尻挙二返云々」を引いて、「皆其歌ひざま音振に依て負たる名なり」とする。しかし、鍋島家本の神楽歌の歌いざまを古代の歌曲名に当てはめるのはどうか。
カタオロシは、第三句を繰り返す2段構成になっているという特徴がある。琴歌譜の歌譜を見ると、「片降」に続く2段構成の歌は、1段目と2段目の声譜を表す符号は一致する箇所が多い。東遊歌のカタオロシも、江戸時代の譜本を見る限りでは、1段目と2段目の節博士が一致する。このことからも、宣長がいう片方を下ろして歌う音振のこととは考えられない。
記紀の歌曲名は、地名や歌詞、物の名や歌の場から名付けられたものなど様々である。カタオロシも片方を低く下げて歌う意味ではなく、場の状況を表す歌曲名であることを考察する。カタオロシは夷振之片下に由来し、場の切り変わりの退場する時や中座する時に歌われ、一旦退場させる、一旦幕を降ろすという意味の歌曲名になっていることを論じたい。
【研究発表3】久米歌の歌い方とそれが意味するもの
歴史民俗博物館名誉教授 小島美子
『日本書紀』は久米歌について「今、楽府に此の歌を奏ふときには、猶手量の大きさ小ささ、及び音声の巨さ細き有り。此古の遺式なり。」(日本古典文学大系)と述べている。この「手量の大きさ小ささ」についてこれまで多くの解釈がされてきたが、土橋寛の「手を打って、拍子を取る時の間(ま)の大小の意か」(『古代歌謡集』の校注 日本古典文学大系)とするのが正しいと私は考える。「歌を奏ふとき」のことばの流れとしても自然であるが、楽器のないときには手を打って拍子を取るのが時代を越えて普通である。その一拍一拍の長さ(間)が等しいのが普通に歌われていた歌のリズムであるのに対して、久米歌はその間に伸び縮みがあるというのである。つまり日本民謡の追分のようなリズム、音楽用語で言えば自由リズムやフリーリズム、より性格にいえば拍そのものが意識されていないという意味で無拍のリズムということである。
日本古典文学では音楽について感想などを述べている例はきわめて多いが、このように音楽の要素や技法について述べている例はきわめて珍しい。それにもかかわらず『書紀』がそれを述べているのは、それまでヤマトの人々の歌にはなかったフリーリズムが初めて現れたからである。これは久米歌以前のヤマトの人々の基本的リズム感は等伯のリズム感であったことも示しており、日本の音楽史にとってきわめて重大な指摘である。フリーリズムは現代に至るまで日本音楽の重要な要素になっているのである。
それをすでに音楽の役所ともいえる楽府の人々が、音楽的に捉えており、『書紀』の執筆者も意識して書いているのである。
このリズムがヤマトの人々にとって新しいリズムであるということは、久米族の人々は新しい渡来民族であるということを意味する。後には大伴連に隷属し、軍事的な部民になったが、靫部として弓術をよくした武官だったともいわれ、北方系の人々かもしれない。