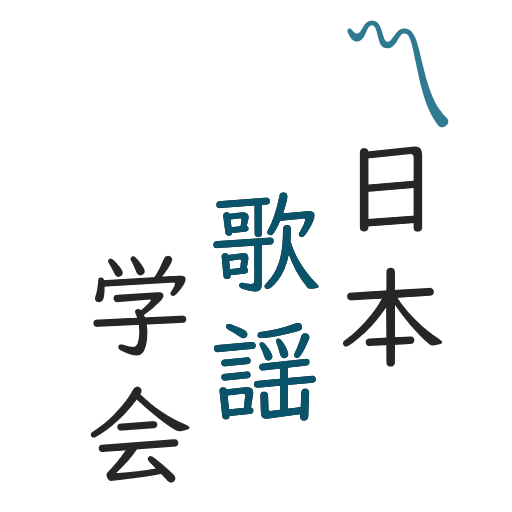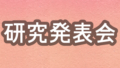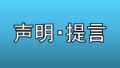| 期日 | 令和7年 5月17日(土)18日(日) |
| 会場 | 立命館大学衣笠キャンパス(Zoom併用) |
【1日目】公開芸能実演・公開講演会
17日(土)12時~17時30分
●役員会(至徳館302会議室)(12時~12時40分)(※理事・評議員・監査の方のみ)
●公開芸能実演・公開講演会(立命館大学アート・リサーチセンター二階多目的ルーム)(13時~17時30分)
・開会の辞 日本歌謡学会会長 立命館大学 辻浩和
・会場校挨拶(ビデオ上映) 立命館大学文学部長 遠藤英樹
○公開芸能実演 常磐津節「恨葛露濡衣」 (13時10分~15時30分)
※共催:立命館大学アート・リサーチセンター
※当日、会場内において常磐津都㐂蔵氏所蔵の出語り図コレクションを展示いたします。
・司会 清泉女子大学 姫野敦子
・解説 南山大学名誉教授 安田文吉
・実演 三味線 常磐津都㐂蔵
上調子 常磐津都瑛太
浄瑠璃 常磐津都史
常磐津都吉
常磐津都清太夫
(*出演者は変更される場合があります)
・トーク・質疑応答
〇休憩(15時30分~15時50分)
〇公開講演会 (15時50分~17時30分)
1、『源氏物語』「末摘花」巻における「衛門府風俗」の引用
・・・早稲田大学 山﨑薫
2、トン族の「上桃園」と歌掛け―中国貴州省錦屏県平秋鎮石引村の事例を中心に―
・・・ 関西外国語大学 牛承彪
●懇親会(NOVECCHIO 円町)
*JR円町駅徒歩一分。会場からはバスで一〇分程度。
参加費 6,000円 (学生で会員の方は3,000円)
【二日目】研究発表会・総会
18日(日)10時~15時(創思館カンファレンスルーム)
●研究発表 午前の部(十時~十二時)
1、連事・立合・猿楽の類型性
・・・國學院大學大学院生 宮嶋隆輔
2、大嘗祭における久米舞の性質について
・・・立命館大学大学院生 砂田和輝
3、琴歌譜の縁記について―その役割と構成―
・・・甲南高等学校・中学校非常勤講師 福原佐知子
●研究発表 午後の部(十三時~十四時二十分)
4、琉球古典箏曲《對馬節》の類歌続考
・・・関西外国語大学 井口はる菜
5、「大報恩寺仏体内所現歌謡」再考
・・・共立女子短期大学名誉教授 菅野扶美
●総会(十四時二十分~十四時五十分)
●閉会の辞 獨協大学名誉教授 飯島一彦
※春季大会にご参加の方は、対面・リモート参加を問わず、下記URLのグーグルフォームからお申し込み下さい。リモート参加の方は5月14日までにお願いいたします。対面で一般参加の方は、お申し込みがなくても参加可能ですが、レジュメ等の用意がありますので、できるだけ事前のお申し込みをお願いいたします。
https://forms.gle/HSEzFQxPYUWo1wEW7
下記のQRコードからもアクセス出来ます。

※リモート参加の方には、5月15日をめどに、メールでZOOMのURLをお知らせします。レジュメはgoogleドライブにアップロードし、各自でダウンロード・印刷していただく形になります(ご参加はお申し込みの方に限ります。また、レジュメの目的外使用や参加者以外への送付は禁止します)。
※1日目の会場は、資料保護のため会場内での飲食ができません(水分補給は可)。昼食は済ませてきていただくか、学内のベンチ等でおとりください。なお、当日学内の食堂・売店は閉まっております。正門・東門付近にコンビニや若干の飲食店はございます。
【問い合わせ先】
日本歌謡学会事務局
〒603‐8577
京都市北区等持院北町56-1
立命館大学文学部辻浩和研究室内
075‐466-3565(電話、研究室直通)
nkayoug2024@gmail.com(メール)
会場アクセス
キャンパスマップ
講演・研究発表要旨
◆5月17日(土)公開講演会
【講演1】
『源氏物語』「末摘花」巻における「衛門府風俗」の引用
早稲田大学 山﨑薫
『源氏物語』には催馬楽をはじめとする多くの歌謡の引用が見られる。それらは、しばしば物語の展開と密接にかかわって機能している。
本講演では、『源氏物語』「末摘花」巻の歌謡の引用について取り上げる。「末摘花」巻には、光源氏が「ただ、梅の花の、色のごと、三笠の山の、をとめをば、すてて」と歌唱する場面があり、古来、難解な箇所として議論されてきた。『花鳥余情』において指摘されている通り、ここで引用されているものと類似した詞章「多多良女乃。花乃如加以祢利好牟夜。滅紫色好牟夜。(たたらめの花の如かいねり好むや滅紫色好むや)」が、『政事要略』に「衛門府風俗」として記載されている。この「たたらめの花」について、先行研究では、「かいねり好むや」という詞章や末摘花の鼻の色などから、紅色の花として考察されていることが多い。しかしながら、詞章は「滅紫色好むや」と続いているため、「たたらめの花」は紅色の花も滅紫色の花もつける植物であると考えられる。滅紫色については諸説あるが、『政事要略』の記述から、少なくとも平安中期にはこの歌謡の「滅紫色」は薄紅色として捉えられていることが分かる。
「末摘花」巻においては、大半の写本で「たたうめ」と詞章が引用されている。梅の花であれば紅色の花も薄紅色の花もつけるという点や、「末摘花」巻の末尾で梅の花と末摘花が重ね合わせられているという点から、誤写等ではなく、「ただ、梅」の意味で詞章が引用されていると考えられる。物語では、末摘花から紅色と薄紅色の衣が光源氏に贈られ、それに因んだ和歌の贈答があった直後の場面でこの歌謡の引用があり、末摘花の鼻の色を揶揄するだけではなく、贈られた衣の色を揶揄する表現であると読み取れる。さらに、「滅紫色」が紫草を用いた染色であることから、「衛門府風俗」の引用は「末摘花」巻に見られる末摘花と紫の君、紅と紫の対比という文脈の中にも組み込まれて機能していると考えられる。
【講演2】
トン族の「上桃園」と歌掛け―中国貴州省錦屏県平秋鎮石引村の事例を中心に―
関西外国語大学 牛承彪
中国貴州省のトン族地域に「上桃園」という習俗がある。旧暦の七月十日から十五日の期間中に行なわれるが、七月十五日は中元節にあたり、現地では「鬼節」また「七月半」と呼ばれる。この日は冥界の門が大きく開き、祖霊は自分の子孫の所に戻って祭祀を受けるとされている。夜になると、女性たちを中心に人々が集まり、厠の神を迎え、衆人の見守る中、脱魂状態に入った女性(霊魂)は冥界めぐりをする。
冥界めぐりをする場所は二か所あるが、一つは村の空間であり、もう一つは「桃園」という理想郷である。村の空間を回るのは、さまよう生者の魂魄を救出するためである。魂魄をその人の家に送ったり、その場にいる親類に渡したりする。
その続きで「桃園」という異空間を旅するのであるが、この過程で歌掛けが見られる。ほかの歌掛けの場合と異なり、歌い手がトランス(脱魂)状態になっていることが特色である。すなわち脱魂状態になった「霊魂」が「桃園」に赴き、その異空間の若者(神仙)と歌を掛け合うのである。
本発表では二つの事例を取り上げて考察を行う。一つは脱魂者が桃園の美景と素晴らしい男子を求めてどんどん桃園の奥の方に進むケースであり、歌詞内容も前へ進もうとする決意ととどめようとする気持ちを表したものである。もう一つは脱魂者が桃園の若者との恋愛を演じ、人々は人間と神仙の恋愛過程を楽しむものである。いずれもその場に即して即興的に歌っている。メロディーや歌詞内容は山や市などで自然発生的に展開する歌掛け(「玩山涼月」)のものと基本的に一致する。歌掛けは「上桃園」において不可欠であり、歌掛けによって桃園巡りが進められている。
「上桃園」は一種の娯楽であるが、厠神を迎える習俗や「地府」の他界観など、外部の影響を受けながら、トン族固有の他界観と融合したものであり、文化的要素が豊富にみられる事例である。
◆5月18日(日)研究発表
●午前の部
【研究発表1】
連事・立合・猿楽の類型性
國學院大學大学院生 宮嶋隆輔
「能」大成以前の要素を残す猿楽系の芸能(いわゆる古猿楽)として、「翁面」(翁)のほかに「風流」(文献上の初出は宝治元年(一二四七)『三会定一記』)や「連事」(初出は建武元年(一三三四)『丹後国分寺建武再興縁起』)、「立合」(初出は貞和五年(一三四九)『春日若宮臨時祭記』)が知られている。本発表では「連事」(多武峰・興福寺の延年。A)と「立合」(大和猿楽・春日田楽・美濃長瀧寺修正会。B)、さらに地方の修正会系祭礼(民俗芸能)に伝わる「猿楽」(遠江の神沢・懐山のおくない、駿河の滝沢田遊び、奥三河の古戸田楽。C)を取りあげる。三種の芸能間の関連性については、これまであまり検討されていないが、佐々木聖佳氏は春日田楽(B立合)と懐山おくない(C猿楽)の詞章に一部類似が見られることを指摘している(「春日田楽詞章考」『日本歌謡研究』五一号、二〇一一年)。そこで本発表では、A連事・B立合・C猿楽の比較検討を行い、以下の共通項を指摘する。
1.問答と歌謡によって進行する猿楽系の芸能 ―A連事・B立合・C猿楽
2.四人の芸能者が方形に立ち、順に一節ずつ歌う ―B立合・C猿楽
3.冒頭部で寺社・行事を讃嘆する ―A連事・B立合
4.問答による題目の設定 ―A連事・B立合・C猿楽
5.皆で歌い囃すことで奇瑞が起こるとする台詞 ―A連事・C猿楽
6.白拍子系歌謡 ―A連事・B立合・C猿楽
三種の芸能に含まれる要素(芸態・詞章・構成等)には、上記のような複雑な連関性が見て取れる。連事・立合・猿楽の類型性を指摘することで、芸能の名称や地域の差異を超えた比較研究の可能性を示す。
【研究発表2】
大嘗祭における久米舞の性質について
立命館大学大学院生 砂田和輝
論者はこれまで、『日本書紀』編纂当時における「来目歌」と舞の関係や、『日本書紀』から『続日本紀』、『東大寺要録』に至るまでに久米舞の担い手が交代したという点について論じてきた。今回は、『続日本紀』、『東大寺要録』から確認できる久米舞が大嘗祭に取り入れられるまでの経緯について、平安朝期の衛府による奏楽や舞の記事に注目しながら考察したい。
『日本後紀』以降の六国史からは衛府による奏楽が行われたことが確認でき、これを以て、雅楽寮の衰退や雅楽寮と衛府との間で管掌する舞楽の住み分けがなされたことなどが論じられてきた。この点について、東大寺大仏の開眼供養会で久米舞を担当した大伴伯麿が後に衛門督となったことや隼人舞を担う隼人司が衛門府の管轄下に置かれていたことを考えあわせると、在来の地方の舞を衛門府が管掌したことが契機となって後の衛府による奏楽が起こったことが想定される。
また、『中右記』からは振鉾の担い手である藤原宗輔が近衛府の次官であり武官であること、『塵袋』からは振鉾=厭舞は邪鬼を祓うという性質をもつものとされていることが確認できる。『日本書紀』には、大伴氏の祖である道臣命は来目部の祖である大来目部を率いて「諷歌・倒語を以ちて妖気を掃蕩へり」とあり、「来目歌」にともなった久米舞にも振鉾と類似の性質があることが考えられる。
『貞観儀式』以降の儀式書に記される大嘗祭儀によると、久米舞は卯の日の神事終了後の午の日の節会で伴・佐伯氏によって舞われたとされる。従来、久米舞の奏上については服属儀礼としての側面が指摘されてきたが、むしろ災いを退け祓い清める性質をもつ舞として大嘗祭に取り入れられたものと考えられよう。
以上のように、久米舞は軍事を担当する衛府の武官によって継承され、災いを退け祓い清める性質を持つ舞として大嘗祭に取り入れられたということを論じる。
【研究発表3】
琴歌譜の縁記について―その役割と構成―
甲南高等学校・中学校非常勤講師 福原佐知子
琴歌譜は一九曲二二首のうち、七曲一〇首に縁記を有している。歌の由縁を記す「縁記」は、後世の音楽書である教訓抄や体源抄も楽曲の由来や口伝を記しているように、琴歌譜も音楽書としての形式を持つと考えられる。
琴歌譜の正月元日節の「長埴安扶理」の後に、「自余小歌同十一月節」とあることから、琴歌譜には「小歌」が何曲かあることがわかる。一方で、奥書に「仍自大歌師前丹波掾多安樹手伝写」とあることから大歌師の多安樹の所持本であり、奥書の日付「天元四年十月廿一日」は小野宮年中行事が記す「大歌始」の日にあたる。そして、琴歌譜の十一月節、正月元日節、七日節、十六日節は、大歌の奏上される節日と一致することにより、琴歌譜は大歌として四節会で奏上されたと考えられるのである。
本発表では、琴歌譜が四節会において、大歌が天皇に奏上されるものであったことをふまえ、天皇作歌であるものを正統な縁記と位置づけている事を示したい。琴歌譜の縁記には、その記載される位置に特徴がある。それは、歌譜の前に記されるものと、歌譜の後に記されるものがあることである。先行研究では、引用文献のない「無名縁記」について、もっとも正伝たる縁起、独自の縁起であるとする論があるものの、それ以外の縁記の位置づけについては論じられていない。
琴歌譜の縁記は、天皇作歌であることを示す歌の格付けをするために、記紀やその他の伝承を載せたものであり、縁記を有する歌が大歌として認識されていたものと思われる。縁記を記載する位置にも琴歌譜著者の見解があり、歌譜の前に置かれている縁記は、無名縁記に限らず、天皇作歌であると記載され、認識されているものである。それに対して、歌譜の後に置かれている縁記は、記紀に天皇以外の作歌者として載るものと、記紀以外の伝承で天皇作歌と伝えているものである。
琴歌譜が四節会で天皇に奏上されるものだからこそ、縁記に天皇作歌であるものとする由緒を求め、大歌として伝えられたのである
●午後の部
【研究発表4】
琉球古典箏曲《對馬節》の類歌続考
関西外国語大学 井口はる菜
『日本歌謡研究』第六一号(二〇二一年)に発表した拙稿「琉球古典箏曲「歌物」三曲の類歌関連歌謡をめぐって」において、琉球古典箏曲の「歌物」の類歌関連歌謡をそれぞれ調査した成果を発表した。その時点では、《對馬節》の詞章で歌われる「つしま」が「対馬」か「津島」か、いずれか明らかにならないまま、従来、類歌関連歌謡として指摘されていた『対馬民謡集』などに確認できる長崎県対馬の「鍛冶屋節」のほかに、大分県佐伯市に伝わる堅田踊の「対馬」や三宅島の「つゝま節」、八丈島の「ツヽシマ節」といった民謡に類歌があることを突きとめたところまでの研究成果であった。しかし、その後も追跡調査していたところ、今回新たな類歌関連歌謡と、その歌にまつわるいくつかの情報を探り当てた。
まず、《對馬節》の類歌が土佐・伊予で歌われていたことを発見し、その周辺を調査した。土佐一条家に関する文書を探したところ、『大海集』(土佐国群書類従五十七伝記部十九所収)や、『皆山集』(高知県の古記録などを収録した史料集)等には、一六世紀に土佐で活躍した公家・大名で、キリシタンでもあったとして知られる一条兼定と、「雪」という名の女性とのエピソードがこの歌の誕生に関わっていると記されている。この歌は「津島節」と言うらしく、これまで謎だった「つしま」について、発表者はこの歌に歌われる愛媛県の津島である可能性を見込んでいる。更に『大海集』において、土佐清水港に漂着した琉球船がその歌を琉球へ伝えたのではないかということがわかる記述も発見した。
今回発見した情報は、この歌が琉球古典箏曲《對馬節》の原曲であるという直接的根拠にはならないと思うが、日本本土で歌われていたこの歌の詞章と琉球との接点としては非常に有力な情報にあたると思われる。従って、本発表では今回新たに判明したことをまとめて紹介し、琉球古典箏曲《對馬節》の類歌にまつわる周辺事情を考察する。
【研究発表5】
「大報恩寺仏体内所現歌謡」再考
共立女子短期大学名誉教授 菅野扶美
千本釈迦堂大報恩寺の釈迦十代弟子像の一つ、阿難陀像の胎内納入品は、大正七、八年の解体修理時に発見され、その内、十九首の歌謡から成る一紙について、大正十二年四月『心の花』第三百号に「大報恩寺仏体内所現の和讃」として佐々木信綱の、「大報恩寺仏体内所現和讃考証」として志田義秀の論文によって、広く世間に紹介された。戦後『続日本歌謡集成』巻一に「大報恩寺仏体内所現歌謡」として収録され、以来今様資料として認知されて久しいが、大報恩寺の成立・定着に関わる人的関係から本今様を読み解く論はまだ出ていないようだ。
大報恩寺は、縁起では藤原秀衡孫とされる求法上人義空が承久二年(一二二〇)仮堂を建て、最終的に安貞元年(一二二七)十二月に三間四面の伽藍を建立、釈迦如来、弥勒文殊の脇侍、十弟子像を安置したとされる。今様もその頃の書写になるものだろう。
ところで十弟子像の一人目犍蓮の足枘には、仏師快慶の墨書、台座には「正三位行兵部卿藤原朝臣忠行」の銘がある。忠行は季行の孫、敦家系篳篥を技とし、後白河院の死に素服を賜った人で、郢曲の二条・楊梅家の祖である。その人物が快慶と共に大報恩寺創建に関わっている。胎内納入品の一つ実尊願文の実尊は、松殿基房の息子で興福寺別当になるがこの人も関わっている。また大報恩寺二世の澄空は実尊の甥(松殿師家男)にあたるが、義空の師、安居院澄憲・聖覚父子に師事し、かつ浄土宗も兼学し、千本釈迦念仏を始めたとされる。後白河院及び松殿家に繋がり、安居院澄憲・聖覚を仰ぐ人々のもとで大報恩寺ができようとしている、その中の今様であることの意味は積極的に捉えたい。
更に問題としたいのは、本今様が『心の花』の二論文以来「和讃」とされ、それが踏襲されて諸書で「法華経和讃」と称されている点である。和讃ではなく今様法文歌であるとの認識をこの場で共にし、後白河院が目指した通りの今様の役割(法文歌、聖教の文に離れたる事なし・今様を歌ふともなどか蓮台の迎へに預らざらむ)が実現していたことを確認したい。